四柱推命とは
八字(はちじ)としての命式の仕組み
「四柱推命」は別名「八字」ともいい、8つの漢字でその人の命式を表す。その仕組みは、生まれた年(年柱)、生まれた月(月柱)、生まれた日(日柱)、生まれた時間(時柱)で4本の柱ができ、それぞれの柱は十干十二支の2つの漢字の組み合わせによってできている。各柱の上にある十干は「天干」といい、下にある十二支を「地支」という。
【表】四柱推命の命式例
| 四柱 | 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 |
| 天干 | 庚 | 己 | 庚 | 丁 |
| 地支 | 午 | 巳 | 戌 | 亥 |
4(年×月×日×時)×2(天干+地支)=8(八字=四柱推命)
日本の干支(えと)と四柱推命の干支(かんし)の違い
日本では、「干支」と書くと「えと」と読み、1年ごとにめぐる十二支の動物をいう。一方、四柱推命の「干支」は「かんし」と読み、十干と十二支を組み合わせた2つの漢字の組み合わせを示している。
例えば、2025年は「乙巳(きのとみ)」の年である。日本では、天干の「乙」は表に出ることは少なく、十二支だけを見て「今年の干支(えと)は巳(へび)」と言う。日本の干支(えと)が表す期間は、現行太陽暦の毎年1月1日〜12月31日である。
四柱推命では、「乙巳」の「乙」という天干の十干と、「巳」という地支の十二支の両方を見る必要があり、「2025年の年柱の干支(かんし)は乙巳」と認識する。四柱推命の暦は、太陰太陽暦(農暦・夏歴)であり、寅月の立春の節入り時刻を1年の始まりとする。2025年の乙巳の期間は、2025年の2月3日23時10分〜2026年2月4日5時2分までである。節入りの日時は毎年変わるので、確認が必要である。
四柱推命と十干十二支
十干十二支とは、いつごろ出来たものだろうか。古代中国の伝説において、河図(かと)と洛書(らくしょ)の発見があり、これにより五行の相生相剋の関係が見出された。十干十二支は、古代中国の黄帝の時代(BC2510年~2448年)、”大撓(だいどう)が、黄帝の命により「五行の情を採り、北斗七星の建するところを占って、十干十二支を制定したとされる(五行大義)」。”(※1)
十干とは
十干とは各柱の上にあり「天干」と言う。十干は「天」の気を表し「陽」を意味する。五行の「木火土金水」を「陰」と「陽」にわけて10種類となる。陽と陰が交互にならぶ。その順序は、奇数に陽を配し、偶数に陰を配す。
【表】十干と陰陽五行
| 1.甲(きのえ/こう)陽木 | 2.乙(きのと/おつ)陰木 |
| 3.丙(ひのえ/へい)陽火 | 4.丁(ひのと/てい)陰火 |
| 5.戊(つちのえ/ぼ)陽土 | 6.己(つちのと/き)陰土 |
| 7.庚(かのえ/こう)陽金 | 8.辛(かのと/しん)陰金 |
| 9.壬(みずのえ/じん)陽水 | 10.癸(みずのと/き)陰水 |
十干は、東西南北の「四方」をなす。
南:丙丁
東:甲乙 中央:戊己 西:庚辛
北:壬癸
天干と天体の配置
現行の太陽暦(グレゴリオ暦)ではなく、太陰太陽暦(旧暦・農暦)の太陽暦を基準に、機械的に循環する記号である。十干の一つひとつは、自然界における季節の象意を持ち、暦にも使われる記号である。しかし、暦の年月日時に十干が配されているが、暦にある十干の象意と実際の季節や宇宙の天体配置との関連はない。年干・月干は地球の公転周期、日干・時干は地球の時点周期にを基準に暦が切り替わる。この詳細については、本ブログ記事内「地支と天体の配置」で解説する。
天干の原義
干支の名称の原義は、樹木の幹(干)と枝(支)であり、その原義を、『四柱推命大全』(※2より)、以下引用する。(※変換できなかった漢字は平仮名で記載)
【表】天干の原義
| 甲 (きのえ/こう) | 甲はひらく(裂けて出てくる)ことをあらわす。草木が大地を破って萌芽(ほうが・草木の芽の萌え出ること)した状態をいう。 |
| 乙 (きのと/おつ) | 草木が初めて生まれ、枝葉(しよう)が柔軟に屈曲した象形となる状態をいう。 |
| 丙 (ひのえ/へい) | 草木が成長して姿形が著明になった状態をあらわす。丙は炳(あき)らかの意であり、「万物成りて炳然(へいぜん)たり」「物皆炳然、著見して而して強大なり」とされる。赫々(かくかく)たる太陽のように燃え上がる火の手を意味する。炳然、著名な状態をあらわす。 |
| 丁 (ひのと/てい) | 草木が成長し、身体が丈夫でたくましく元気な状態である強壮(長壮・ちょうそう)をあらわしている。また、壮丁(そうてい)を意味し、労役・軍役にあたる成年に達した男子を意味する。 |
| 戊 (つちのえ/ぼ) | 茂るの意味。大地の草木の繁茂(はんも)(茂盛・もせい)を象徴している。 |
| 己 (つちのと/き) | 紀の意味。万物には形があり、紀識(書き記す)できる。 |
| 庚 (かのえ/こう) | 更の意味。秋收(しゅうしゅう)(秋の収穫)をして、来春を待つ。 |
| 辛 (かのと/しん) | 痛の意味。季節(気節)の変化、万物の勢いが衰える凋零(ちょうれい)を意味する。 |
| 壬 (みずのえ/じん) | 妊(にん)の意味。気が地中に潜み、新しい生命を育み孕育(よういく)する。 |
| 癸 (みずのと/き) | 揆(き)の意味。草木が地中において培養され、出る時を待ちながら、推し量ることである。 |
【表】十干と自然界の象徴
| 甲 | 大木(剛直) |
| 乙 | つる草・湿木・柔 |
| 丙 | 太陽(光) |
| 丁 | 炎(焚き火・燭・灯火・暖炉) |
| 戊 | 燥土(山、丘、砂石) |
| 己 | 湿土(田園の土) |
| 庚 | 剛斧(剛健・堅い) |
| 辛 | 宝珠(柔弱) |
| 壬 | 大河・大洋(雄大な水) |
| 癸 | 雨(春)・露(夏)・霜(秋)・雪(冬) |
十二支とは
十二支は各柱の下にあり、「地支」と言う。「地」の気を表し「陰」を意味する。「子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥」の十二支である。陽と陰が交互にならぶ。その順序は、奇数に陽を配し、偶数に陰を配す。
四柱推命の命式では、年、月、日、時間のそれぞれに十二支が存在する。それぞれの柱の地支は、天体の周期と関連がある。
【表】十二支と陰陽五行
| 1. 子(ね) | 陽水 |
| 2. 丑(うし) | 陰土 |
| 3. 寅(とら) | 陽木 |
| 4. 卯(う) | 陰木 |
| 5. 辰(たつ) | 陽土 |
| 6. 巳(み) | 陰火 |
| 7. 午(うま) | 陽火 |
| 8. 未(ひつじ) | 陰土 |
| 9. 申(さる) | 陽金 |
| 10. 酉(とり) | 陰金 |
| 11. 戌(いぬ) | 陽土 |
| 12. 亥(い) | 陰水 |
地支の原義
地支とは、樹木の枝や根を意味し、支とは、支えるもの、見えないもの、端、分かれたものを意味する。十二支に()内の各動物を割り当てたものを十二生肖(じゅうにせいしょう)という。”古来より、命書(四柱推命の本)の中で十二生肖についての多くの意義を含む解釈がされてきたが、こじつけが多く、信じるに値しない内容である。なぜなら、十二生肖は、生まれた年を記憶しやすいように動物に割り当てた、順序を表す記号にすぎない。”と鐘進添老師は言及している(※3)以下、『四柱推命大全』より、地支の原義を引用する。
【表】地支の原義
| 子 | しげるの意味で、草木の種子が土中の水気を吸いて滋潤(じじゅん・うるおうこと)となる。 |
| 丑 | 草木は土中で出芽(植物が芽を出すこと)する意味で、その形状は屈曲している。 |
| 寅 | 演う(おこなう)の意味であり、屈曲し、寒土の中の草木は、温和な陽春(陽気のみちた暖かい春)に遇(もてな)されて、地上に伸長生長(しんちょうせいちょう)する。 |
| 卯 | 冒う(おおう)の意味であり、旭日(きょくじつ)(朝日)が東天(とうてん)(東の空)より躍り出て、万物を滋(ますます)茂らせる現象である。 |
| 辰 | 震えるの意味で、万物が震えて起きる時季の現象である。 |
| 巳 | 万物が成熟期に到ることで、暫時(ざんじ)の静止状態をあらわしている。 |
| 午 | 陽気が極盛(きょくせい)し、陰陽の分岐点に到る状態をあらわしている。 |
| 未 | 味という意味で、草木の果実がだんだんと熟成していく過程において、滋味(じみ)(栄養があって味のいいこと)をつけていく段階をあらわしている。 |
| 申 | 果実が熟成した現象である。 |
| 酉 | 醸す(かもす)の意味で、太陽が西に沈みこむように、果実が既に熟成し、発酵していくことをあらわしている。 |
| 戌 | 滅という意味であり、草木が凋零(ちょうれい)し、生気が絶滅することをあらわしている。 |
| 亥 | 核(さね)(果実の中心にある種子を保護している堅い部分)という意味で、万物が収蔵され、草木の種子が土中において蔵され、春を待つ段階である。 |
【表】十二支と五行(季節)
各五行は基本的にそれぞれ陰と陽の2つの十二支が存在するが、土だけは4つある。水、木、火、金は四季を表し、土は季節の変わり目である。
| 亥・子 | 水(冬) |
| 寅・卯 | 木(春) |
| 巳・午 | 火(夏) |
| 申・酉 | 金(秋) |
| 丑・辰・未・戌 | 土(土用〜季節の変わり目) |
【表】十二支と四季と方位(五行)
土の十二支(丑、辰、未、戌)は、地支の四季を言及する時、前月の季節に属す。四柱推命の命運において、四季を表す3つの十二支が集まることを「三会(さんかい)」といい、その季節の五行のエネルギーが極めて強くなる現象が起きる。四季の土の気は、その季節の最後にはいる。
| 亥・子・丑 | 冬(水)・北 |
| 寅・卯・辰 | 春(木)・東 |
| 巳・午・未 | 夏(火)・南 |
| 申・酉・戌 | 秋(金)・西 |
地支の暦と天体の配置
天干と地支が結びつき、一つの柱ができあがる。4つの天干である年干・時干・日干・時干は、地球の公転周期、及び、自転周期に基づいた暦の中で、機械的に循環するものであり、宇宙の天体配置とは関連がない。一方、地支の一部には、実際の天体配置との関連性がある。現行の太陽暦においては、年支、及び、日支は、天干と同じく天体配置とは関連がない機械的に循環する記号である。一方、月支、及び、時支は太陽と地球との関係に基づいた暦と連動している。月支の十二支を見れば何月かわかり、時支の十二支を見れば何時かわかる。4つの天干(年干・時干・日干・時干)、及び、年支・日支は、季節や時間による感覚的な判断はできない。農暦の法則によってできており、暦の法則をすべて暗記しているのでなければ、万年暦等を確認しなければわからない。
■年支
年支は、地球の公転周期と関連づけられている。四柱推命においては、年の切り替わりを 立春の節入りの瞬間(おおむね2月4日頃) とし、その時点から年柱が定まり命式が組み立てられる。
十二支は1年ごとに割り当てられ、この1年のサイクルを「歳(さい)」と呼ぶ。この「歳」という概念は、歳星(木星)の運行速度に由来する。木星は太陽の周りを約11.862年かけて公転するため、地球から見るとおよそ1年ごとに黄道十二星座をひとつずつ移動していくように見える。そこで古代の天文学では、木星の軌道を十二等分し、それぞれに十二支を対応させた。しかし、木星は西から東へ反時計回りに移動するため、実際の観測と暦を合わせるために「大歳(たいさい)」という仮想の星を設定し、これを時計回りに配置することで 太歳紀年法 が成立した。
木星の公転周期は正確には11.862年であるため、古代より暦の調整が必要とされてきた。漢代には補正が行われていたが、現行の暦では調整は行われておらず、太陽暦の1年単位で干支が機械的に循環する仕組み となっている。(※4)そのため、実際の木星の運行と暦上の干支の巡りは完全には一致していない。
また、四柱推命における 1年の始まりは「寅月(2月)」の節入り(立春) とされる。したがって、1月1日から立春前に生まれた者は、年柱を前年の干支として命式を立てることになる。
■月支
月支は、地球の公転周期に基づいて定められている。地球が太陽の周りを1年(365.2422日)かけて公転する運動を24分割したものが 二十四節気 であり、四柱推命ではこの節入りから次の節入り前までをひと月とみなし、そこに十二支を配置する。
月柱を決める際には、暦の月初ではなく、節入りの正確な日時を基準とする。たとえば、立春の節入りが2月4日の午前10時であれば、その瞬間から新しい月が始まる。したがって、1日から節入り直前に生まれた者は、前月の十二支を月柱とする。
月支が示す十二支には、それぞれ季節の意味と五行の性質があり、命式の「格局」を判断する上で特に重要な要素となる。四柱推命において月支は、年支よりも具体的に季節感や環境を反映する指標であり、その人物の命式全体を読むうえで重要な役割を担う。
| 十二支 | 期間 |
|---|---|
| 寅 | 2月(立春〜啓蟄に入る前) |
| 卯 | 3月(啓蟄〜清明に入る前) |
| 辰 | 4月(清明〜立夏に入る前) |
| 巳 | 5月(立夏〜芒種に入る前) |
| 午 | 6月(芒種〜小暑に入る前) |
| 未 | 7月(小暑〜立秋に入る前) |
| 申 | 8月(立秋〜白露に入る前) |
| 酉 | 9月(白露〜寒露に入る前) |
| 戌 | 10月(寒露〜立冬に入る前) |
| 亥 | 11月(立冬〜大雪に入る前) |
| 子 | 12月(大雪〜小寒に入る前) |
| 丑 | 1月(小寒〜立春に入る前) |
■日支
日支は、地球の 自転周期 と結びついている。地球が一度自転する時間、すなわち24時間を1日として区切り、これを基準に十二支を割り当てる。
ただし、四柱推命における1日の切り替えは、暦上の午前0時ではなく、前日の23時(子の刻) とされる。このため、23時から24時の間に生まれた場合、その日の干支ではなく、翌日の日干支が日柱として用いられる。日支は、命式の中でも「日干(=自分自身)」を支える重要な役割を担う。
■時支
時支は、地球の 自転周期 と関係している。地球が一回自転する24時間を12等分し、それぞれに十二支を割り当てている。これにより、1つの支はおよそ2時間を表す。
| 十二支 | 時間 |
|---|---|
| 子 | 23時〜1時 |
| 丑 | 1時〜3時 |
| 寅 | 3時〜5時 |
| 卯 | 5時〜7時 |
| 辰 | 7時〜9時 |
| 巳 | 9時〜11時 |
| 午 | 11時〜13時 |
| 未 | 13時〜15時 |
| 申 | 15時〜17時 |
| 酉 | 17時〜19時 |
| 戌 | 19時〜21時 |
| 亥 | 21時〜23時 |
四柱推命では、時刻を単純に時計の時刻で判断するのではなく、実際の太陽の動き(真太陽時) を基準にする。そのため、命式を出す際には「時差修正」を行い時柱を求める。修正には次の2種類がある。
- 経度による時差修正
標準時線(日本なら東経135度)から、生まれた地点がどれだけ経度で離れているかをもとに修正する。経度15度で約1時間、1度で約4分の時差が生じる。 - 均時差による修正
均時差とは、地球の自転速度と太陽の見かけの動きのずれによって生じる「実際の太陽時(真太陽時)」と「平均太陽時(標準の時計時刻)」との差を指す。1日を24時間と定めている基準は「平均太陽」であり、これは一定速度で動く仮想的な太陽である。しかし、実際の太陽は季節によって南中(太陽が真南に到達する時刻)が前後する。この時間のずれを均時差と呼ぶ。均時差は年間を通じて ±約15分 の範囲で変動する。例えば、ある日は「正午(12:00)」のはずの南中が11時45分となる場合もあれば、12時15分となる場合もある。この現象は、地球の軌道が楕円であることと地軸の傾きによって生じる。
こうした補正を経て、真太陽時を割り出し、その時間帯に対応する干支を時柱とする。
四柱推命の干支(かんし)は、別名「六十甲子(ろくじっこうし)」
十干と十二支の組み合わせには明確なルールがあり、陽干は陽支と、陰干は陰支と結びつく。陽干と陰支、陰干と陽支の組み合わせは存在しない。この原則により、十干と十二支の60通りの組み合わせが成立する。よって、四柱推命の干支(かんし)は、別名「六十甲子」とも言う。
十干の数は10、十二支の数は12であり、両者の最小公倍数は60である。この60種類の組み合わせが一巡すると、六十甲子は再び始まり、永遠に循環する。木星の公転周期は約12年、土星の公転周期は約30年であり、これらの最小公倍数も60年であることから、古代中国では木星と土星の運行が六十甲子の原理と考えられている(※5)。しかし、現代における六十甲子の暦は、実際の木星と土星の会合周期とは一致していない。
空亡
天干は10種類、十二支は12種類存在する。天干の十干が一巡した際に、割り当てられなかった2つの干支を「空亡」と呼ぶ。個人の命式における空亡は、日柱の六十甲子から判断される。日柱の六十甲子が一巡して割り当てられなかった干支が、その人にとっての「空亡」となる。「空亡」の解釈は、流派や鑑定者によって異なる見解があるが、四柱推命では基本的に、「空亡となる干支の持つエネルギーが半減し、弱まっている状態」と考える。
| 六十甲子 | 空亡 |
|---|---|
| 甲子, 乙丑, 丙寅, 丁卯, 戊辰, 己巳, 庚午, 辛未, 壬申, 癸酉 | 戌亥 |
| 甲戌, 乙亥, 丙子, 丁丑, 戊寅, 己卯, 庚辰, 辛巳, 壬午, 癸未 | 申酉 |
| 甲申, 乙酉, 丙戌, 丁亥, 戊子, 己丑, 庚寅, 辛卯, 壬辰, 癸巳 | 午未 |
| 甲午, 乙未, 丙申, 丁酉, 戊戌, 己亥, 庚子, 辛丑, 壬寅, 癸卯 | 辰巳 |
| 甲辰, 乙巳, 丙午, 丁未, 戊申, 己酉, 庚戌, 辛亥, 壬子, 癸丑 | 寅卯 |
| 甲寅, 乙卯, 丙辰, 丁巳, 戊午, 己未, 庚申, 辛酉, 壬戌, 癸亥 | 子丑 |
例えば、日柱が「甲子」(六十甲子の最初)の人にとっての空亡は「戌」と「亥」であり、日柱が「癸亥」(六十甲子の最後)の人の空亡は「子」と「丑」となる。自分にとって空亡となる十二支が命式にある場合や、行運で巡ってくる際には、その地支が命運に与える影響が弱いと判断される。
六十甲子(十干十二支)は、四柱推命を読み解く「記号」である
四柱推命の命式を構成する十干と十二支(六十甲子)の基本理論を解説した。命式を理解するためには、命式で使われている十干十二支がどのようなものであるかを知る必要がある。「干支」という記号の意味が分かれば、人の「命(めい)」がどのように決まるのか理解できる。
「月支」と「時支」は、その人が生まれた瞬間の地球と太陽の天体配置によって決まる。しかし、「年支」「日支」、および「四柱の天干(年干・時干・日干・時干)」は、宇宙の天体配置とは直接関連しない。また、月支は暦上の月とリンクしているが、四柱推命の鑑定方法は、中国的季節感が当てはまらない赤道付近や南半球でも全世界共通で適用される。四柱推命の世界では、例えば南国で生まれても、12月は冬であり寒くて土も凍る。南半球で雪の降る季節に生まれても、7月生まれは火の季節に生まれたとされる。十干や十二支は季節の循環を象徴する意味を持つが、どれも命運を読み解くための「記号」に過ぎない。現実の自然や季節とは関係がなく、四柱推命という仮想化された空間での象意として理解されるべきである。
四柱推命は、自然界の循環の法則に基づいて人の命運を論理的に推論する技術である。命運の解説ではありありとした自然の風景が詩的に映し出されることもあるが、実際の天体配置や居住地域の自然環境が与える影響を直接扱うものではない。もちろん、私たちは現実世界の影響も受けるが、それは四柱推命の命運判断とは別の要素である。命式の八字(十干十二支)は、自然界の観察から導かれた宇宙の原理に基づき、その人の人生に起こりうる可能性を論理的かつ客観的に推論するための「記号」である。北半球で発展したことから北半球の季節感で説明される部分もあるが、鑑定結果は世界共通であり、表面的には北半球の自然を見ているように思えても、奥深い部分では宇宙の法則が含まれているのだろう。
四柱推命や風水では、同じ記号が使われることもあるが、長い歴史の中で発展した技術であり、鑑定法や流派によって意味や定義が異なることがある。命式を読み解く際は、記号の定義を理解した上で判断することが重要である。この文章は、中国清朝宮廷の流れをくむ台湾の鍾進添(しょうしんてん)老師の高弟である山道帰一先生の四柱推命講義を受講した筆者が、山道先生の著書や翻訳書、講義内容を基に執筆したものである。
参考文献
※1 山道帰一(2009).『完全定本【実践】地理風水大全』.p68.河出書房新社.
※2 鍾進添. 山道帰一(翻訳) (2023).『完全定本 四柱推命大全』.p25.河出書房新社.
※3 鍾進添. 山道帰一(翻訳) (2023).『完全定本 四柱推命大全』.p25.河出書房新社.
※4 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「大歳」
※5 鍾進添. 山道帰一(翻訳) (2023).『完全定本 四柱推命大全』.p28.河出書房新社.
東道里璃 (とうどう りり)
最新記事 by 東道里璃 (とうどう りり) (全て見る)
- 変えられない間取りと、変えられる環境― 風水学の実践が明らかにする、環境と行動の関係 - 2026年1月9日
- 【週刊タイムス住宅新聞 掲載】ロンジェ®琉球風水アカデミー受講生のリノベ作品が語る“氣の流れ”の空間美 - 2025年11月7日
- 琉球風水とニライカナイ信仰に久高島で出会う:沖縄思想の源流に触れる旅 - 2025年9月19日
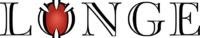


この記事へのコメントはありません。