琉球風水謎解き探検 in 備瀬集落
はじめに
沖縄国際大学の「グローカルセミナーⅠ」において、講師・東道が担当する琉球風水の講義。
第1回目の首里城フィールドワークに続き、2025年4月25日には本部町の備瀬集落を舞台に、学生たちと共に2回目のフィールドワークを実施しました。
本講義前半は、沖縄の歴史文化にフォーカスし、王朝時代の風水思想を軸に沖縄伝統集落の思想的、構造的な街づくりのあり方を座学と体験で学びます。前半の発表テーマは選択式で、以下4種類のカテゴリーを設定しました。
①琉球風水の歴史
②当時の最先端科学としての風水思想とその環境学的な機能性
③景観と思想、信仰、価値観、アイデンティ
④風水の活用法やメリット
自分の興味関心のある領域からテーマを決め、知りたいことを深堀りして発表。備瀬集落を歩くにも、発表という最終的なランディング地点をある程度見据えていれば、フィールドワーク中に自分にとって必要な情報が見えてきます。
今回は「琉球風水謎解き探検」と題し、学生自身が風水理論を手掛かりに集落の景観を読み解くことを目的としました。
備瀬集落の概要と学術的背景
備瀬は「伝統的集落景観保存地区」として知られ、沖縄における原風景を今に伝える貴重な集落です。
家々を守るように植えられたフクギ並木は、台風からの防風林として機能するとともに、日差しを遮る緑のトンネルをつくり、独特の集落景観を形づくっています。
このフクギの植栽配置は、自然が作り出す美しさに加え「家を護り、風を制御し、集落全体を調和させる」という風水思想と重なる実践知といえます。
学習課題と「謎解き探検」
備瀬集落の琉球風水謎解き探検では「備瀬集落の玄武と朱雀を探し当てる」というミッションを設定。制限時間1時間で備瀬集落内を歩き、答えを探し出します。学生9名を3人づつ3グループに分け、地図とコンパスをもって各グループで探します。
スタート、及び、ゴール地点は、公民館前。備瀬集落は、難易度をABCで表現すると「Bクラスのやや難しめ」。学生たちにとって、簡単なのか、難し過ぎるのかは想像もできませんでした。あっさり見つけられちゃうかもしれないし、全然見つけられないかもしれない。忠実に風水理論に従えば、答えが出せる仕組みになっています。ただし、風水集落の解読には応用力が必要です。
この「風水ミッション」は、自ら風水理論を使いこなして景観を読み解く探究学習です。
探索の様子と学生の気づき
さて、結果はいかに。
制限時間の少し前に学生たちが公民館の前に戻ってきました。
「おかえりなさい」と言って出迎えると
「先生、この講義、めっちゃ楽しいです♪」と
風水集落散策をかなり楽しんできた様子でした。
「玄武と朱雀は見つけられましたか」と聞くと、
全員が「見つかりませんでした」との回答。
そこで、公民館の前で、スタート時にヒントの意味で出した内容を再びレクチャー。そして、風水理論のおさらいをし、理論をこの現場でどのように使うことができるのか話をしました。
「先生、スタートの時に話してくれた内容は重要なヒントだったんですね」と、50分近くもの間、探し歩いてきたからこそ、ヒントの意味の重要さが実感できたようです。
そして、玄武の見える地点まで歩いて行きました。
「玄武の見える人いますか」
と聞くと、わからない様子。
「風水メガネを持っている人はいますか」
と聞くと、「はい、持ってます。でも、先生、このメガネ1,600円でしたが大丈夫でしょうか?」と、ジョークのセンスは最高に際立っています。
が、「メガネ」の意味が違います。
「風水メガネ」とは、脳のフィルターです。
脳は見たいものしか見えない。
知識があり、意識しているものしか見えない。
首里城の玄武を思い出してもらい、
「似たような風景は見えませんか」
「四神を見る時は、亀の甲羅を探してみましょう」
「四神を探す時は、どこに背中を向けますか」
などのヒントは与えていくと
「あ〜、あれだ」と気づく学生が数名でてきました。
続いて、朱雀のポイントへ。
「朱雀は見えますか」
と聞くと、これはみんなだいたいわかっている様子。
「では、朱雀はどれですか」
と聞くと、ちょっと考えて
「先生、全部です」との答え。
「はい、確かに全部ですが、具体的には何ですか」
「首里城の朱雀と似ているのは、どのあたりですか」
「鳳凰が、飛び立てそうな地形ですか」
などの対話をしながら、四神への理解を深めていきました。
学術的考察 ― フィールドで確かめる風水理論
風水は「迷信」ではなく、環境学・景観学としての合理性を備えています。
フィールドワークでは「答え」を教えるのではなく、伝えたのは「風水理論とその使い方」です。本人が実際にその理論を現場で使って答えを導き出すことで、「風水理論は再現性のある科学である」ということを実感してもらうのが目的でした。理論の再現性をフィールドで確認できることこそ、風水を学術的に位置づけるうえで重要です。
クラスメイトと自然の中を歩くのはとても楽しかったようです。「玄武や朱雀を初めから教えてもらうのではなく、自分たちで探すというのが、面白かったです」との意見があり、ここがポイントだったと思います。風水はフィールドワークでしか伝えられないことも多いです。私が教育で大切にしているのは「発見の喜び」です。
次のフィールドワーク地点へ移動。備瀬集落出口にサーターアンダギーの屋台があり、みんなでできたてをほおばりながら海洋博公園へ。一生懸命に玄武と朱雀を探したご褒美です。たくさん歩いた後の甘いものは、きっと美味しかったんじゃないかと思います。
まとめと今後の展開
今回のフィールドワークを通して、学生たちは備瀬集落を「観光地」としてではなく「風水的景観を読み解くフィールド」として体験しました。
そこに広がるのは、生活に根ざした知恵と、自然と調和する設計思想。まさに琉球風水が伝える空間哲学そのものです。
次回の「グローカルセミナーⅠ」では、おきなわ郷土村にてさらなる実地学習を予定しています。
琉球風水を現場で確かめる学びは続いていきます。
東道里璃 (とうどう りり)
最新記事 by 東道里璃 (とうどう りり) (全て見る)
- 『中城御殿御敷替御普請日記』解読への道:琉球風水の粋を極めた「世子の空間」を読み解く - 2026年1月30日
- 2026年タイムス住宅新聞・年始特集「理(ことわり)と美の風水史」:首里城・中城御殿から繋ぐ300年の時間と空間 - 2026年1月30日
- 変えられない間取りと、変えられる環境― 風水学の実践が明らかにする、環境と行動の関係 - 2026年1月9日
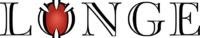


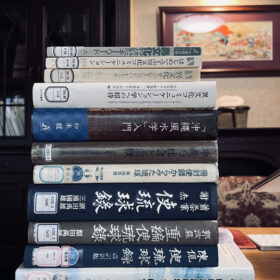

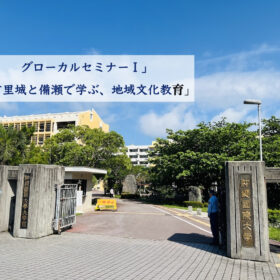

この記事へのコメントはありません。